
「風の谷のナウシカ」はこの「虫めづる姫君」のお話からヒントを得たそうですよ。
『堤中納言物語』虫めづる姫君 その1 の原文冒頭
この姫君ののたまふこと、「人びとの、花、蝶やとめづるこそ、はかなくあやしけれ。
人はまことあり。本地(ほんぢ)たづねたるこそ、心ばへをかしけれ」とて、よろづの虫のおそろしげなるをとりあつめて、「これが成らむさまを見む」とて、さまざまなる籠箱どもに入れさせたまふ。「中にも、かは虫の心ふかきさましたるこそ心にくけれ」とて、明け暮れは、耳はさみをして、手のうらにそへふせてまぼりたまふ。

『堤中納言物語』虫めづる姫君 その1 のあらすじ
普通は蝶々や花を好きになるのが年ごろの姫様。なのに、この姫君は虫が好き。周囲の女房たちに見せては怖がらせて毎日お屋敷は大騒ぎ。
『堤中納言物語』虫めづる姫君 その1 の現代語訳
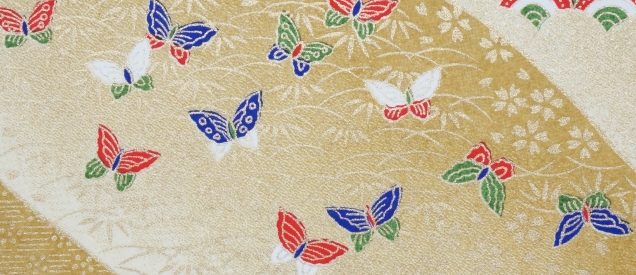
蝶が大好きなお姫様がお住まいのお屋敷のすぐ近くに、按察使の大納言のお姫様のお屋敷がありました。
按察使の大納言のお姫様は、
奥ゆかしくて、特別すばらしいご様子の方で、
両親からもそれはそれは大切に育てられておりました。
この姫君が言われることには、
きれいだかわいいとかわいがるのって、
バカみたいで私には理解できない。
不思議でたまらないわ。
本質のところを極めてこそ、
その心遣いにもほんとうの趣があるはずよ。
と、お隣の蝶を愛でるお姫様や、
世間一般の方々とはちょっと違っていたのです。
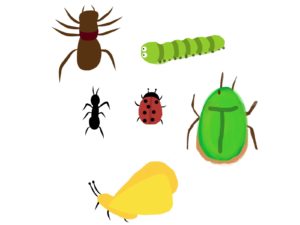 いろいろな虫の、とくに気味悪そうなのを集めては、
いろいろな虫の、とくに気味悪そうなのを集めては、
と言って、召使に、さまざまな籠や箱に入れさせていたの。
中でも毛虫が一番のお気に入り。

ものごとをふか~く考えてる様子で、趣があるわぁ。
明けても暮れても、髪の毛を耳にかけて、
毛虫を手のひらの上にはわせては、
じいっとご覧になっていらっしゃいます。
ほんとうにお好きなんですね。

若い召使の女性たちは虫を怖がってうろたえてしまいます。
それで、身分が低くてあんまり怖がらない男の子をお呼びになって、
箱の虫たちを取り出して、
名前を尋ねたりしています。
男の子たちも初めて見るような虫には、
姫様は、新しく名前をつけて楽しんでいらっしゃいます。

着飾ったりしない、ありのままの姿がいいってことよ。
年頃女性ならみんなしているお歯黒はもっとだめ。

白い歯を見せて笑いながら、虫たちを、
朝から晩までかわいがっていらっしゃいます。
普通のお姫様とはあまりに違いすぎますね。
若い召使たちが、怖がってうろたえて逃げ回っているので、
姫君のお部屋はいつも大騒ぎ。
姫君は、異様なほどに大きな声で召使たちを叱ったりしています。
こんなふうに怖がる召使たちにむかって、姫君は、
下品よ。
召使たちは、困り果てて、ますますうろたえてしまっています。
平安時代のお化粧方法は?


お顔を思いっきり白く塗って、眉はそりおとし、
上のほうに2つの丸をはき墨でかく。
男性も同じような化粧をしていたようです。
しかも夜まで化粧したまま。
おしろいには鉛が含まれていたので、貴族たちの健康には、よくなかったようです。


ものごとの本質をとらえていて、
どきっとしますね。
『堤中納言物語』虫めづる姫君 その1 の原文
この姫君ののたまふこと、「人々の、花、蝶やとめづるこそ、はかなくあやしけれ。人は、まことあり、本地たづねたるこそ、心ばへをかしけれ」とて、よろづの虫の、恐ろしげなるを取り集めて、「これが、成らむさまを見む」とて、さまざまなる籠箱どもに入れさせたまふ。中にも「烏毛虫の、心深きさましたるこそ心にくけれ」とて、明け暮れは、耳はさみをして、手のうらにそへふせて、まぼりたまふ。
若き人々はおぢ惑ひければ、男の童の、ものおぢせず、いふかひなきを召し寄せて、箱の虫どもを取らせ、名を問ひ聞き、いま新しきには名をつけて、興じたたまふ。
「人はすべて、つくろふところあるはわろし」とて、眉さらに抜きたまはず。歯黒め、「さらにうるさし、きたなし」とて、つけたまはず。いと白らかに笑みつつ、この虫どもを、朝夕に愛したまふ。人々おぢわびて過ぐれば、その御方は、いとあやしくなむののしりける。かくおづる人をば、「けしからず、ぼうぞくなり」とて、いと眉黒にてなむ睨みたまひけるに、いとど心地惑ひける

